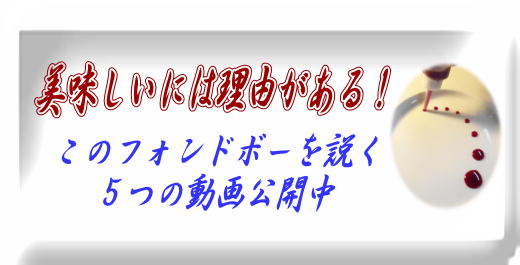毎日の食事のこと、どれくらい知っていま すか?お米の銘柄

毎日の食事のこと、どれくらい知っていま すか?お米の銘柄 関連動画
レシピは下部にあります。
日本の主食であるお米。北は北海道から南は沖縄まで、日本全国でさまざまな銘柄の稲が栽培されています。
お米といえば、コシヒカリと思われる方も多いのではないでしょうか。
そのコシヒカリは昭和28年に福井県で育種され、昭和31年にその名前が付けられました。
優れた食味が認められ昭和54年には作付面積トップとなり、今なおその地位を守り続けています。
いまや、全国各地でつくられているコシヒカリですが、繰り返し栽培されることで、
地域ごろに異なる特性があらわれています。
お米を評価する指標として「食味」があります。
食味とは、口の中で感じる味だけでなく、かみごたえ、見た目、においといった5項目があり、
これらのバランスがとれたものが美味しいお米だと評価されます。
コシヒカリは粘りが強く、香り、味のバランスがもっともよいとされ、
冷めてももちもちとした感じが残ります。
|
|
おにぎりにするなど、白米そのものを味わうのに適しています。
ひとめぼれはコシヒカリによく煮えいます。香り、甘味、うまみなどのバランスがよく、
冷めても固くなりにくいのが特徴です。濃い目の味付けの洋風料理やお弁当にあいます。
あきたこまちはくせがなく、水分が多いのでやわらかいお米です。
とても粘りがつよいので、冷めても美味しくいただけます。
ササニシキは粘りが少なく、さっぱりすることから、
お酢が染み込みやすいので酢飯にするのに向いています。おかずを引き立たせるので、和食、中華にもぴったりです。
このように、お米の品種ごとに食味の特徴と調理の適正があることが分かります。
また、同じ銘柄だったとしても、育つ環境によってお米の食味は変化します。気象だけでなく、
土壌が豊かで水質がよいことも大切な条件です。土壌や気象にあわせても品種改良をされることが多いので、まずは地元のお米に注目してみるのも良いかもしれません。

材料(4人分人分)
金芽米 長野県産コシヒカリ / 購入時付属の金芽米専用カップで2カップ
水 / 400ml
レシピを考えた人のコメント
お米大好き一家です!5年くらい前から土鍋でご飯を炊いています。金芽米を食べて、みんな元気いっぱい!食事の基本、米と味噌でバランスよく必要栄養素を補給!
詳細を楽天レシピで見る→
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
↓↓ ポイントが貯まるレシピ サイト ↓↓
>>最短約 30 秒!▼無料▼会員登録<<
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…