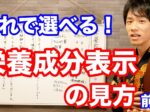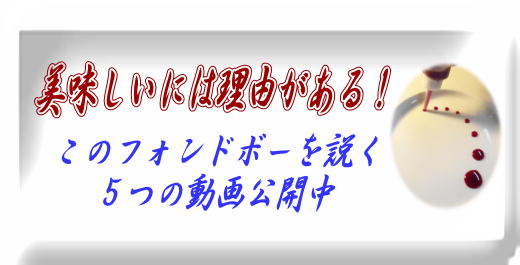家庭でも発生します、気を付けたい食中毒

家庭でも発生します、気を付けたい食中毒 関連動画
レシピは下部にあります。
食中毒、と聞くと、学校給食や飲食店などで食べる食事が原因になるイメージが強いかもしれませんが、
実は家庭での食事が原因となる食中毒も発生しています。
家庭での食中毒を防ぐのは、食材を購入し、調理するみなさん自身です。
食中毒を引き起こすのは、「細菌」と「ウィルス」です。
目には見えない小さなものですが、条件がそろうと食べ物の中で繁殖し、
それを食べることによって食中毒を引き起こします。
細菌が原因となる食中毒は特に夏場に多く、
出血性大腸菌やカンピロバクター、サルモネラ菌などが代表的なものです。
一方、低温や乾燥した環境でも長く生存することができる
ウィルスが原因となる食中毒は冬場に多く発生します。
原因となる代表的ものはノロウイルスです。
|
|
毒キノコ、フグなどの自然毒、アニサキスなどの寄生虫なども
食中毒の原因となるため、じつは様々な物質によって食中毒は一年中発生しています。
それでは、どのようにして防いだらよいのでしょうか。そのための原則を紹介します。
食中毒予防の原則「つけない」「増やさない」「やっつける」という3つの原則があります。
まずは原因菌やウィルスを「つけない」ために、しっかり手洗いを行いましょう。
また、まな板、包丁といった器具もきれいに洗って使いましょう。
「増やさない」ためには、品温の管理を行いましょう。
肉や魚といった生産食品やお惣菜などは、購入後早く冷蔵庫に入れましょう。
また、早めに食べてしまうことも大切です。
ほとんどの細菌やウィルスは過熱によって死滅します。
中まで加熱をして「やっつける」ことを意識しましょう。
正しい知識をもっていれば、家庭内で食中毒を予防することはそこまで難しいことではありません。
今回紹介した3原則を日々の生活に生かしていただきたいと思います。

材料(4人分)
酢 / 大匙3
塩 / 小さじ1
米ぬか / 大匙1
レシピを考えた人のコメント
できれば除去したいですよね?発がん性のある農薬。野菜の肥料として使用される牛糞は牛の腸管内に常在する病原性大腸菌あり。
詳細を楽天レシピで見る→
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
↓↓ ポイントが貯まるレシピ サイト ↓↓
>>最短約 30 秒!▼無料▼会員登録<<
━━━━━━━━━━━━━━━━━━…